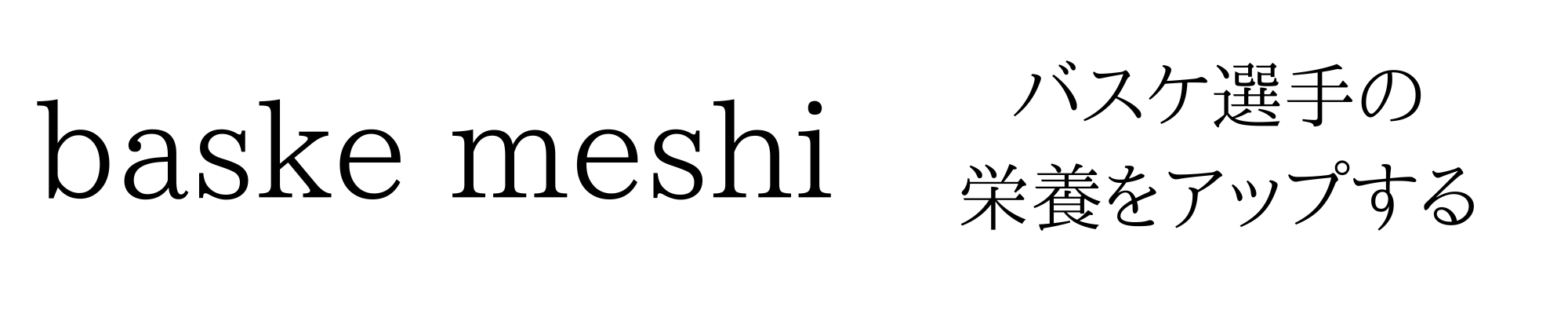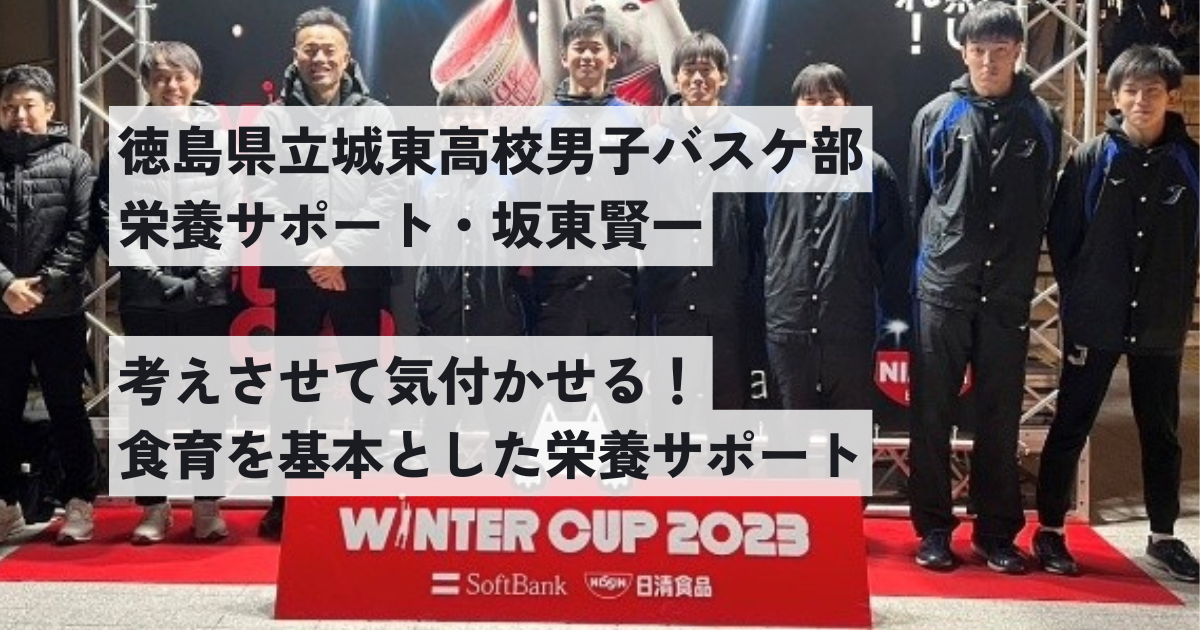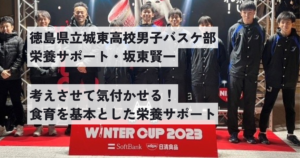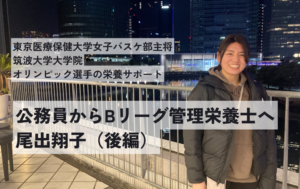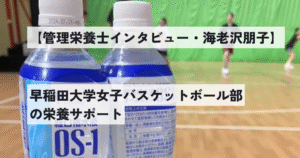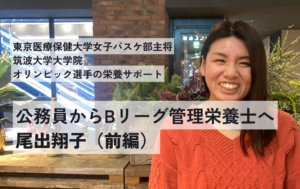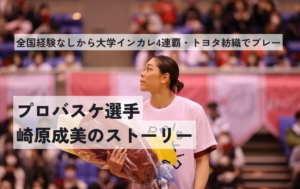徳島県でアスリートの食育に情熱を注ぐ一人の管理栄養士がいる。坂東賢一さんだ。

坂東賢一さんと息子さん
友人の姉がバスケットをやっていたことがきっかけで小学校3年生からバスケットを始めた。小中高とバスケットに打ち込み過去には5回の全国大会出場も果たしたほどの実力者だ。
「ミニバスでは小学校6年生の時にチームメイトに恵まれて全国大会に出られましたね。中学校のときは当時あったジュニアオールスターに徳島県代表に選ばれて全国大会に出場しました。高校の時はインターハイに1回、ウインターカップに2回出られました。」
高校は県内でもトップクラスの進学校である徳島県立城東高校に進学。
入学してすぐの5月、ハードな練習から足首の靭帯を怪我してしまいチーム練習から離れたことがあった。中学と高校ではフィジカルの強さが一段とレベルアップするが、増量がうまくいっていなかったのだという。
「トレーニングも頑張っているのに、なんで(体重が)増えないのかなと考えたときに、食事が重要なんじゃないかと思ったんです。」
このとき身体作りと栄養の関係について興味を持った。
管理栄養士という職業を知ったのは高校1年の冬。テレビで管理栄養士のドキュメンタリー番組を見たことがきっかけで管理栄養士を目指すことに。
「医師や看護師は治療はできても予防はできないじゃないですか。管理栄養士は食で病気の予防が出来るんですよ。予防できた方が絶対いいじゃないですか。」
病気の予防に関わることができる管理栄養士という職業に魅力を感じていたが、このときはまだスポーツ栄養士になるとは思っていなかったそう。
「当時はまだ日本でスポーツ栄養士という職業自体も知られてなくて、プロ野球チームに一人いるくらい。狭き門すぎてなれるなんて思ってなかったんですよ。」
高校卒業後は四国大学生活科学部管理栄養士養成課程(現 健康栄養学科)に進む。ここで現在の活動の中心となる「食育」と出会う。
「僕が入学した2005年はちょうど食育基本法ができた頃で、新しく栄養教諭の免許が取れるようになったんですよ。栄養教諭の免許を取得するための授業の中で、栄養のことは勿論ですが、教育とか指導といった『食育』の大切さに気付いて興味を持ったんです。」
食育基本法とは、2005年に公布された「食育に関する基本理念や施策」を定めた法律のことで、食育とは「生きる上での基本」と位置づけ、「国民の健康や豊かな人間形成」を目的としている。と記されている。
また坂東さんが代表を務める「食結び」さんのYouTubeでは「食育=病気の予防」と定義している。スポーツをするにしても趣味を楽しむにしても、豊かな人生を送るには健康な身体があることがベースであり、それを育むのが食育なのだ。
大学を卒業後、徳島県内の小学校で憧れの栄養職員として勤務し始める。
新たに「食育」を推進していくという立場で働いたが、当時は「食育」という言葉が今ほど浸透しておらず、職員からは抵抗を示す声もあったそう。
「もともとないものを一から構築することはとても大変なことでしたね。先生方の中には新しいことをあまり好まない人もいました。」
まず食育とはどういうことをするのか理解してもらうところからだった。
そうして壁にぶつかりながらも子供たちへの食育に注力した。
給食に残食が多いメニューがあったとき、坂東さんは授業で子供たちにこう語りかけた。
「皆は日本に生まれたからこうやって何の不自由もなくご飯が食べられているけどな、世界には食べられなくて死んでいく子供たちもいるんだ。皆はどう思う?」
世界の飢餓と日本のフードロスという二つの問題をかけ合わせて授業を行った。飢餓で苦しむ世界の子供たちの写真なども見てもらったという。
すると、自然に子供たちの食行動に変化が現れ、残食が減っていったのだ。
「一番大切なことは子供たちに考えさせて、気付かせること」
これが食育で最も大切なことだ。
食育に奮闘する毎日を送っていたある日、日常が一変する。
父が体調を崩してしまったのだ。実家は自営業だったため、仕事を辞めて家業を手伝うか、管理栄養士を続けるか選択しなければならなくなった。
「管理栄養士を辞めるか家業を手伝うかかなり迷いましたけど、僕は長男なんでね。家業を手伝うことにしました。」
そうして管理栄養士を退職。一旦はキャリアが途絶えたが、食育への情熱がなくなることはなくFacebookで食育に関する情報発信を続けた。
すると、食育に関する講演依頼が来るようになったのだ。
そこからフリーランスの管理栄養士として活動の幅を広げ、知人が保育園を開業したときは最初から食育で関わらせてもらえることにもなった。
小学校の栄養職員をしていたときは、一から新しいものを作り出すのに苦労した経験がある。
「今回は、『食育に力を入れる保育園ですよ』という認識を最初から持ってもらうために職員の新人研修で食育講座の時間をつくってもらい、お話させてもらいました。」
スポーツ栄養士としての最初の活動は後輩がコーチを務める中学バスケ部への栄養セミナーだった。
「後輩も最初は『栄養士に何ができるんだ?』って感じだったと思うんですよ。でもコンディション管理とかフィジカル強化とか栄養が必要な部分はたくさんあるので、それを総動員してセミナーをやりました。」
その後、母校の城東高校男子バスケ部から栄養サポートの依頼があり、6年間選手をサポートした。
コロナ禍では試合会場に入れる人数にも制限があったことから、アシスタントコーチとして登録してもらい管理栄養士という立場を越えてチームを支えた。
当時の栄養サポートをこう振り返る。
「高校生はやっぱり増量、フィジカル強化が課題でしたね。最初は食事調査から始めました。3日間の食事を写真で撮ってもらって栄養価計算して評価しました。結構量は食べられているのに体重が増えない子もいて、『何でかな?』と思ったらやっぱり問題は栄養バランスだったんですよね。いくら量を食べていても代謝を促すビタミン類を摂取できていないと吸収されていかないじゃないですか。」
こういった課題解決のために栄養講習会を頻繁に行ったという。

「講習会を頻繁にやっていましたね。初めは月1回を3か月くらい続けました。何かのデータで見たんですけど、ヒトは2週間くらいしか意識が続かないらしいんですよ。なのでその後も定期的に講習会を行っていました。」
ここでも大切にしていたことは食育。
今自分に必要なことは何なのか、選手自身に考えさせて気付かせることだ。
「高校は教育機関という役割もあるので、答えを与えるのではなく気付かせることを意識していました。僕は食育を重要視していたのでそこがマッチしたのかもしれないですね。必要な栄養情報は伝えて、何を選んだらよいかなどは選手たちに考えさせていました。自分で考えて分からなくなったらLINEで聞いてもらっていましたね。」
選手への栄養講習会に加えて、定期的に開かれる保護者会で栄養情報の共有もした。
城東高校はほとんどの生徒が自宅から通学しているため、実際に食事を準備することが多い保護者の協力が不可欠なのだ。
「具体的にはn-3系脂肪酸の摂取量が少なかったので魚を積極的に摂ってほしい旨を伝えたりしていました。」
こうしたサポートもあって増量がうまくいく選手も出てきてはいたが、城東高校は県立の進学校。
他の強豪校と違って身長の高い選手や実力のある選手が集まっているわけではないため、全国で勝つための課題はまだまだたくさんあった。
「高校生の練習ってめっちゃ走るじゃないですか。身長の高さがあったら練習のランメニューを少なくしてセットプレー増やしても上を目指せると思うんですけど、徳島のバスケはいかんせん小っちゃくて細くて走れない。それでも全国で勝てるようになるにはまず練習をしなくちゃならないですから、そこを信じてやっていましたね。」
ハードな練習からエネルギー消費量が摂取量を上回ってしまい増量できない選手も中にはいたという。
また進学校ならではの課題もあった。
「進学校なので練習が終わってから塾で勉強をする子もいるんですよ。そうすると夕食を食べる時間が遅くなってしまう。それでも選手たちはよく食べてくれていたんですけど、次の日の朝ごはんを食べられなくなる子が出てきたんですよ。そういうときには胃に負担をかけないような食べ方や摂取量、消化に良いものなどをアドバイスしたりすることはありましたね。」
本来なら、身体を大きくするために練習量を減らして睡眠時間をしっかり取ることや、食べたものの消化吸収に時間を取ることが必要だと坂東さんは考えていたが、学生競技は時間に限りがある。
全国で勝つためにはどうしてもハードな練習をしなければならないし増量も必要。でも勉強も疎かにはできない。
坂東さんもそれはよく分かっていたが、そういった状況のなかでコンディション調整と増量を達成することの難しさを感じていたという。
「なかには1日にご飯を8合食べてた選手もいましたね。それでも増量できなくて泣くんですよ。それで試合では自分より身体の大きい選手と戦わなきゃいけないので、とにかく頑張っている選手たちに寄り添っていましたね。」
初めてスタッフとして関わったチーム。選手たちと悔しさも味わった。
「県大会の決勝で負けて全国逃した時とかは本当に悔しかったですね。僕も高3のインターハイ予選の決勝で負けて全国を逃したことがあるんですけど、それと同じくらい悔しかったです。もう1週間くらい放心状態でした。選手たちには勝たせてやりたい…勝たせてやりたいはおかしいね。目標を達成してほしかったですね。」
一方でこんな嬉しいエピソードもあった。
「筋肉量が増えたことによってフィジカルが強くなって、今までコンタクトで負けていた選手が踏み込めるようになってレイアップいけるようになったとか、ゴール下から逃げていた子がガツガツいけるようになったとか、プレーの幅が広がっていったのは嬉しかったですね。」
劇的な成長を遂げた選手もいた。
「最初は身体が細くて朝ごはんも食べられなくて嘆いていた子が最後は徳島県で誰にも触れられないくらいフィジカルが強くなったこともありました。その子は月1くらいで食事に関する質問がずっと来ていたんで。やっぱりそういう子は伸びますよね。」
またフィジカル強化によりメンタル面にも良い変化が見られたという。やってきたことが県外のチームに通用したり活躍できたりしたことで選手たちの自信にもつながっていったのだ。
栄養面だけでなくプレー面でも選手からアドバイスを求められることも増えていった。
そうした選手たちのメンタル面の成長を間近で見られたことや、栄養スタッフという立場を超えて一緒に戦えたこと、全国大会出場に貢献できたことは坂東さんにとっても大きな経験になったという。

今後の目標について伺った。
「城東高校で結果を出すことができて、徳島のジュニアアスリートやガンバロウズオルト(B3に所属するプロバスケチームの前身チーム)、あと女子の富岡東高校バスケ部からも依頼が来て栄養サポートを始めました。それから今、徳島のバスケットボール協会の栄養委員もやらせてもらっているんですけど、徳島全体の食のレベルを上げることでもう一歩上の競技レベルに上げていきたいと思っています。」



バスケットだけに限らず、野球チームやバレーボールチームからも栄養サポートの依頼があったという。
しかし管理栄養士一人ではできることに限りがある。
「大学院で行っていた研究でジュニアアスリートに関わることがあったんですけど、現場は栄養を求めていることが分かったんです。でも徳島って本当にスポーツ栄養士いないんですよ。これはスポーツ栄養士を育てなきゃいけないなと思ったんです。僕の分身がおったらいいな~といつも思います(笑)」


「アスリートの栄養サポートをしてきて何にも代えられない貴重な経験をたくさんしてきました。こういったことを将来活躍するスポーツ栄養士さんたちにもぜひ経験してほしいと思います。」
また、スポーツ現場にはエビデンスが求められるため研究は大切なことだという。坂東さんは現在、四国大学の教員として、研究、徳島全体の競技力向上、そしてスポーツ栄養士の育成に奮闘している。
インタビュー・文:田村未来
写真提供:坂東賢一さん

坂東賢一 (Bando Kenichi)
徳島県出身、1986年生まれ。小・中・高とバスケットボールに打ち込み、過去5回全国大会に出場。大学で管理栄養士免許を取得。小学校・大学(支援センター)・病院・スポーツクラブで働き、その経験を経てフリーに転身。四国大学大学院を修了後、現在は四国大学で教員をしながら地元徳島のスポーツチームの栄養サポートに尽力している。