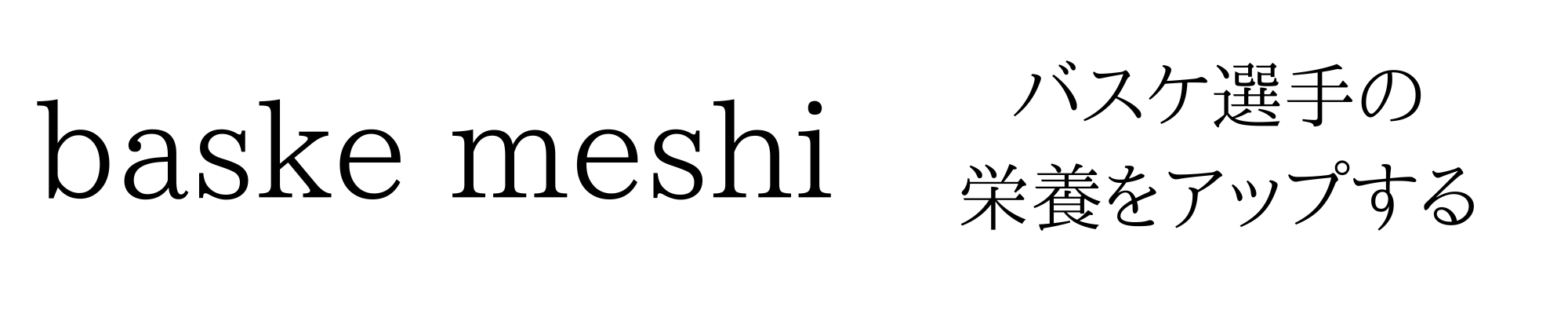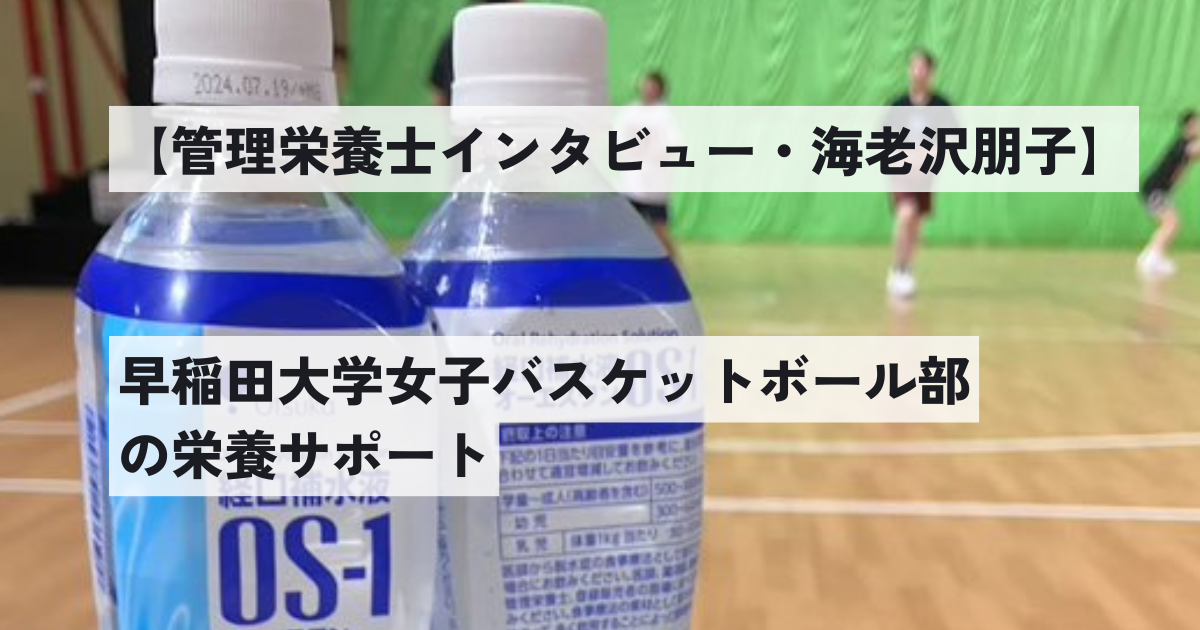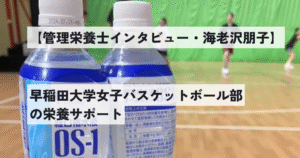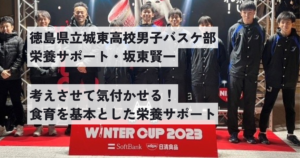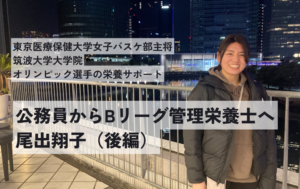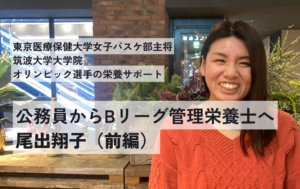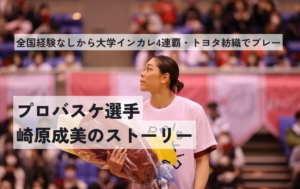今回は、早稲田大学女子バスケットボール部で栄養サポートをされている管理栄養士の海老沢朋子さんに、「大学女子バスケ選手の課題点」や「どのような栄養サポートをされているのか」についてインタビューしました。
――海老沢さんのご経歴を教えてください。
女子栄養大学栄養学部を卒業しました。管理栄養士ではなく栄養士課程の学科だったので、卒業後は給食委託会社に就職し、病院で発注や調理補助などの実務経験を経て、管理栄養士の国家試験を受験し合格しました。
管理栄養士免許取得後は、栄養指導やスポーツ栄養に本格的に携わりたいという気持ちが強かったので、特定保健指導や糖尿病重症化予防チームの運営に従事しながら、専門学校のテニス部やスピードスケート選手の栄養サポートを行っていました。
ご縁をいただき、2021年から早稲田大学女子バスケットボール部の栄養サポートを担当しています。
――早稲田大学ではどのような栄養サポートをされているのでしょうか。
トーナメントや新人戦などのスケジュールの合間をぬって、4月から6月の間でセミナーを行っています。全員におさえてほしい内容は全員に、下級生向けには基本的な部分を中心に構成しています。
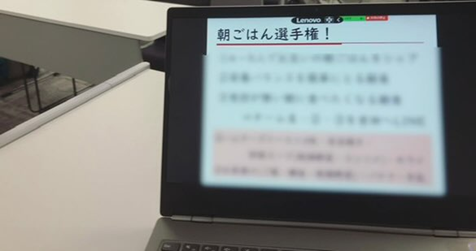
シーズンが始まると食事チェックを開始します。前任の方より継続しているため、チームとして実施することが定着しています。1週間分の食事写真を撮影し、コミュニケーションアプリを通じての共有とフィードバックをする方法をとっています。
ただ、選手と直接コミュニケーションをとって伝えたいこともあるため、1~2週間に1回程度は体育館で直接会話する時間も大切にしています。その際には、練習内容やチーム状況も確認するようにしています。毎日、選手の様子を見ている訳ではないので、より多く時間を共にしている社会人・学生スタッフともコミュニケーションをとって、状況把握をしています。
また、最近は暑くなってきたので体育館の湿度や温度をチェックして選手たちに水分補給を促す声かけもしていますね。


経口補水液が美味しく感じた人は脱水に注意。
食事チェックは、年間を通してコンディション管理をしたいというチームからのニーズもあり、インカレ終了まで毎日行っています。
1人で行っているので大変な面もありますが、試行錯誤しながらやっています。
――選手の栄養面で、特に課題となる部分はありますか。
エネルギー源のなかでも糖質の不足が一番の懸念点ですね。時代の流れもあってたんぱく質は意識して摂っている選手が多いのですが、練習の終了時間が夜遅いので、「夜にご飯を食べると太っちゃう」と思っている子もいて、あまり食べないなど食事にこだわりがある選手もいます。
そういうときは1回切りで説得しようとせず、ゆっくり時間をかけてコミュニケーションをとりながら食べることの必要性を話していますね。
その話ばかりされても嫌になってしまうと思いますし、あえて別の話題を振ったりしてコミュニケーションをとり続けていると、そのうち「最近はちゃんとご飯食べています」「食事抜いてません」と報告をくれることもあります。
しっかり食べられていない選手は、ケガの治りも遅かったり、リハビリが長引いたりしている場合があると、感覚的にですが思います。
逆によく食べられている選手はケガからの復帰も早いですし、身体も強いと感じます。
しっかり食べるための工夫として、昼食から夕食まで時間が長く空いてしまうときは補食を活用するように伝えていますね。
——補食に関してどういったアドバイスをされていますか。
補食に関しては、セミナーで必ず伝えていますね。練習時間が遅く夜型の生活になるので、特に新入生に多いですが、急に体重が増えてしまう子もいます。
そういったときは練習前後に補食を取り入れるよう提案することもあります。
具体例としては、練習前におにぎり1個、練習後にもおにぎり1個食べて、帰宅後には軽めにご飯とおかずを食べる方法です。1回の食事を練習前後と帰宅後の3回に分けて食べるイメージですね。
——食事量に関しては具体的にどのようなアドバイスをされていますか。
セミナーでエネルギーや糖質、たんぱく質の必要量について説明し、選手個々で必要量を計算してもらっています。
「1回の食事でご飯はこのくらい必要だよ」という目安を示し、「今食べている量と大きな差があったら調整が必要かもね」といった話をしたり、例えば800kcalの食事をどのように工夫すれば1000kcalになるかなど写真で示して、「このくらい食べればいいんだ!」というのを視覚的にイメージしてもらったりしています。
1日に必要なエネルギーや栄養素の量については、数字だけで伝えることはしていません。セミナーでも計算していますが、今の体重やプレーの調子とどのくらい食べられているかに合わせて、調整するように伝えています。
計算で出したエネルギーや主食量が必ずしもその選手に合ったものではない可能性もあるので、数字の取り扱いに注意することも併せて伝えています。
選手によってもアプローチは違いますが、エネルギー不足からくる月経不順や貧血を防ぐために、糖質の摂取量が極端に少なくないかは注意して見るようにしています。
——月経不順というお話がありましたが、女性に特に必要な栄養素のお話などもされますか。
セミナーで話す際には、例えば、「鉄を多く摂ったとしても糖質の摂取量が極端に少ない場合だとうまく使われない」など、理由と一緒に伝えることを心がけています。
バスケットと同じで食事も基本に立ち返ることが大事だと感じています。
見た目には不調がないように見えても、実はエネルギーや栄養素が不足している状態で日々プレーをしている選手も少なくありません。
自覚のないままその状態が続いてしまうと、やがてケガやコンディション不良につながる可能性があります。
だからこそ、毎日元気にバスケットを続けるためには、体調管理の一環として食事にも意識を向けることが重要なのです。
——外食やコンビニでの食事に関してアドバイスはありますか。
外食やコンビニで食事を選ぶ際も、バランス良く選ぶことが基本になります。コンビニだと量が少なすぎるケースが多く見られますね。
例えば、サラダスパゲティは食べやすく、野菜もたんぱく質源も多い商品が増えてきてバランスが良さそうですが、選手が摂る量としては糖質が少ないため、おにぎりを追加することをおすすめしています。
また、脂質が少なすぎるときもありますね。意識して低脂質・高たんぱく質なヨーグルトやサラダチキンを選択する選手も多いのですが、他の食品で脂質が摂れていない場合は、補うように伝えることもあります。
外食に関しては、食事のバランスももちろん大事なのですが、仲間と食事を楽しむ時間も大切にしてほしいので、基本的には制限していないですね。
筋肉量を増やしたい、体脂肪を減らしたいなど身体づくりの目的に応じて、「このメニューにしてみたらどう?」や「最近揚げ物が多いから焼き魚に変えてみてね」といった話をすることもあります。
あとは、学生なのでお金との兼ね合いにもなるのですが、定食屋さんでは栄養バランスを良くするためにサラダをつけることやトッピングを活用するように伝えています。
飲み物に関しても、カフェの甘い飲み物を飲んでいるのを見かけることもありますが、選手の状況に応じて柔軟に対応していますね。
——簡単に栄養が摂れる食事ポイントはありますか。
外食でも自炊でも、なるべく“一品でさまざまな食品が摂れるメニュー”をおすすめしています。例えば野菜やたんぱく質源が一度に摂れる鍋料理はとても便利です。
特に一人暮らしの選手には、一石二鳥のようなメニューを提案するようにしています。「食材を組み合わせることで、一品でいろいろな栄養が摂れるよ」といったアドバイスですね。最近は、一人暮らしでも料理好きな選手が多く、調理スキルが高いケースもよく見られます。
それでも、野菜や果物は不足しがちです。そこで「ミニトマトなら洗ってそのまま食べられるよ」とか、「冷凍ブロッコリーを使ってみるといいよ」など、手軽に栄養を補える工夫を伝えています。最近は暑くなってきたので、「冷凍フルーツを活用するのもおすすめだよ」といった季節に合わせたアドバイスも心がけています。
——秋のリーグに向けての食事ポイントはありますか。
まず大切なのは「体重を落とさないこと」です。これは夏休みに限ったことではありませんが、長期休みに入ると朝ゆっくり眠れるため、起きる時間が遅くなり、朝食と昼食が一緒になってしまう選手が増えてきます。
すると、普段よりも運動量は多いにもかかわらず、食事の回数が減ることでエネルギーが不足し、結果的に自然と体重が落ちてしまうケースが多く見られます。
そのため、「しっかり3食を摂り、体重を落とさずにリーグ戦を迎える」ことを毎年の重点ポイントとしています。
また、夏場は特に水分補給の重要性も高まりますので、食事と併せて意識したいですね。
——リーグ中はどのようなことに注意が必要ですか。
数か月に渡るので、終盤に進むにつれて選手の身体は徐々に疲弊し、食欲も落ちやすくなっていきます。
そのため、リカバリーの面では糖質やたんぱく質に加えて、ビタミンやミネラルも意識的に摂取することが大切になります。
また、リーグ序盤では試合で一時的に体重が落ちても、1週間のうちに元に戻るケースが多く見られますが、リーグ後半になると体重がなかなか戻らなくなるタイミングが出てきます。その戻りにくくなるポイントを見逃さないためにも、日々の体重の変化や選手の状態をチェックしていますね。
——試合当日の食事に関してポイントはありますか。
特にリーグ戦の試合時間は週によってバラバラです。遠征で移動を伴う場合や試合前後の時間帯によっては、食事の時間を確保することが難しいケースも多くあります。
そのようなときは、試合前にエネルギー補給を目的におにぎりやエネルギーゼリーなどの糖質を摂り、試合後には素早く疲労回復を促すために、おにぎりやプロテインなどで糖質とたんぱく質を補うように伝えています。
糖質が摂れる食品の一つとして、持ち運びがしやすく、かつビタミン類も摂れる100%果汁のオレンジレンジジュースを取り入れることもおすすめしています。
ただし、試合後1時間以内に食事をとれる状況であれば、補食ではなく通常の食事を優先することが大切だと伝えていますね。


——栄養サポートをしていてやりがいを感じたエピソードはありますか。
栄養サポートに入って一年目のシーズンにインカレで3位になったときは、本当に嬉しかったです。勝った瞬間の選手・スタッフの表情は今でも忘れられません。
また、選手が卒業する際に「『無理なく楽しんで食べてね!』と言ってもらえたおかげで、好きな食べ物を楽しみながらしっかり食事を摂ることができました」と言ってもらえたことが、私にとってとても印象的でした。
栄養サポートにおいては、アスリートに食べてもらうことがスタートになります。エネルギーも栄養素も、食べないことには身体に届きません。
選手たちはコートの中で相手と戦うだけでなく、自分自身の限界とも向き合いながら、頑張っていかないといけない。そんな姿を数多く見てきたからこそ、せめて食事の時間だけはリラックスして、楽しんでほしいと思っていました。その想いが選手に届いていたことを知ったときは嬉しかったですね。
——今後の目標を教えてください。
チームとしての目標は、インカレ優勝です。そのためにも、コンディション管理や栄養管理を”選手全員が自分でやる”という意識を持つことが重要だと考えています。
選手自身が主体的に考え、食事を選択していくことはとても大切だからです。「練習前に補食を食べた方がよく動けた」「試合直前におにぎりを食べるのはお腹が重かったかも」といった体感を通じて、自分の身体や体調と対話できる力をつけていってほしいですね。
そうした力は、チームとして勝ち続けていくコンディション管理のためにも、選手としてはパフォーマンスの向上にもつながるはずです。
それだけではなく、競技を引退した後の人生にも役立つと思っています。笑顔で卒業して、その後の人生にもつながるサポートをしていきたいですね。
インタビュー・文:田村未来
写真提供:海老沢朋子さん

海老沢 朋子(Ebisawa Tomoko)
1994年生まれ。管理栄養士。女子栄養大学栄養学部を卒業後、給食委託会社にて病院給食の実務経験を積んだ後、管理栄養士免許を取得。特定保健指導や糖尿病重症化予防のチーム運営、専門学校テニス部やスピードスケート選手の栄養サポートを経験し、現在は明治安田健康開発財団 健康増進支援センターで勤務しながら早稲田大学女子バスケットボール部の栄養サポートを担当している。